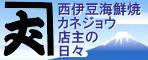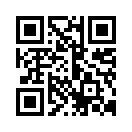2008年04月09日
ヤシャバラ峠越え
写真は記事と関係ありません。郷土史研究
ヤシャバラ峠越え 安良里 藤井徳太郎
安良里の滝ノ前(地名以下同じ)を上がり、三駄木.奥ノ沢を経て標高698.7メートルの
笠蓋山を越すと大久須から大久須川に沿って須鎌を上り茨ノ木・草木ヶ沢の渓谷を延びてきた細道
と合い重なって一本道と成り、ヤシャバラ峠を越えて下り込むと仁科村の祢宜畑の集落に出る。
この大久須ー祢宜畑を結ぶ山径はたいへん便利な近道となって白川・宮ヶ原・大城・祢宜畑を
含む大沢里集落の生活路として利用された。
大沢里からは主に物日(ものび)や物事(ものごと)のある場合には宇久須や定期船を
利用して土肥へ買い物に、宇久須からは行商人やボテー衆(牛馬の売買をする人)が主で頼まれ物や
ニュースも運んだ。この方々が土地の方と顔なじみとなりお茶をご馳走になったり
世間話を交わすうちに真面目な話、真剣な話に進み目出度く縁が結ばれた方々が
あったと。利用する径は違うが田子衆も来たが安良里衆のボテーという話は聞いていない。
伝わってもいない。これは笠蓋山の峻険越えが大儀のため之が出来なかったので
あろうと私の知人(一色在住、文化協会長 )は話された。
西伊豆町誌に・・・最近ではあまり宇久須へ抜ける人もないようですが、
昔はこの道を歩いて宇久須へ嫁いだ人が多くあったそうです。
また浜降り(はまおり)といい亡くなられた人を葬送する一つの習わしを
行うため仁科の浜へ下るよりも早かったこの道を歩いて宇久須の浜まで行ったそうです。
大沢里地区は昔は山仕事従事者が多く、大山信仰(神奈川県伊勢原市 別名雨降山
1,251メートル阿夫利(アフリ)神社)大山講が盛んであった。
麦の収穫も終わり田植えも済んだ七月にどの集落もクジ引きで白川、宮ヶ原は二人、
祢宜畑は四人、山越で宇久須までは徒歩で、それから汽船で沼津まで行き御殿場線に乗って
大山さんへ・・。大山講は茅葺き屋根の葺替え費用の積み立てと大山詣りの旅費助成を
主な事業としていた。クジに当たるということは大変な光栄と集落中の羨望の的になった。
代参人が参拝を終へて翌日同じ道筋を経て帰ってくる日は、女衆は番屋に集まって
例年に倣いボタモチと待ち設け(ご馳走)作りに大騒ぎをしながら張り切った。
帰着した代参人が杖や御札分けが終わると御神酒が廻る。
一杯が二杯と進むと賑やかとなる。
この日は講の祝日とされていた。大山詣りも第二次大戦が始まる前まで行われていたが、
その後は途絶えてしまったという。・・と書き記されている。
八助さんは七〇才の半ばを越していて小柄だが矍鑠(かくしゃく)として一人で
奥山に入り、炭焼きに専念していた。ある晩の夜更け、家の衆が届けてくれた餅を
焼いて食っていた。不図「おじいさんオレにも餅をくれ、餅をくれ」と声がした。
その音声に八助さんは小首を傾げた。「あァ餅か今は食ってしまったから何もない。
あしたの晩来い待っている」と告げた。
翌晩になった。昨晩と同じ時刻に声がした。「待っていた。手を出せ赤い餅だ」
出したその掌に宵の内より炭火で真っ赤に焼いた手頃の石を火箸で挟み載せると同時に
自分の掌も重ね力一パイ包み込んだ。「アッチチチーウウウウー」と悲鳴を挙げながら
「これでは八さんあまりにもひどい」とケモノ語で叫びながら毛深い本来の手を丸出しで
草木を掻き分け山鳴りをして遠ざかっていく怪物に「ざまァみろオレを誤魔化すには
モット勉強してこい。」と大声で怪物の背に叩きつけて大笑いをした。
遅い夕食の弁当を食って一服していたら声がした。「おじいさん祢宜畑へ出るつもりで
来たが、暗くなり道に迷い右往左往していたらアンタの小屋の灯が見えた。やっと此処に
辿りついた。今晩一晩厄介になりたい」あァそりゃァ気の毒だ。泊るといっても
掛けるものも無い。それでも良いか。」「それで結構です。小屋の隅にでも
休ましておくんなさい。」「判った。それではオレの言うこと為すことに文句は無いな。」
「はい」と返事をしながら入ってきた旅人をやにわに有無を言わせず其処にあった荒縄で
十重、二十重に体中に巻き付けて頑丈な生木柱に縛り付けた。
「おじいさん何をするだ。この縄を解いてくれ。解いてくれ。」と涙を出して懇願した。
「何を言うか。お主はオレの言うこと為すことに文句は無いと約束をしたのだ。」
旅人は何回も何回も懇願したが八助さんは頑として受け付けない。
二人は睨み合ったまま刻はたっていた。何時の間にか東の空が明るくなっていた。
小鳥の囀りが聞こえてきた。小屋で飼っていた鶏が鳴いた。やわらかい
日差しが小屋に差し込んできた。八助さんは旅人の縄を解いた。
二人は長いこと力一杯抱き合って大粒の涙を流した。
去ってゆく旅人の背に八助さんは「今度は本当の人間だったなァ」と独り言を言った。
この二つの挿話は平成5年一月103才の賀茂村一番の天寿を全うされ亡くなった宮崎學治郎翁が
一寸と話された物を脚色してみました。
実話のようでもあるし作り話のようでもある。
総ては五十年余前の話です。
平成十三年発行文芸賀茂第30集より 賀茂村文化協会発行
Posted by カネジョウ at 22:23│Comments(4)
│郷土研究
この記事へのコメント
ということは、うちの横の道の話??
仁科に繋がっているとは聞いていたけど、
よくあそこを通ったものだなあと思います。
でも、海沿いよりも、早いってことですよね??
仁科に繋がっているとは聞いていたけど、
よくあそこを通ったものだなあと思います。
でも、海沿いよりも、早いってことですよね??
Posted by たんたん at 2008年04月10日 21:46
at 2008年04月10日 21:46
 at 2008年04月10日 21:46
at 2008年04月10日 21:46たんたんさん毎度です。たんたんさんの所の道を通って行きます。
私もくらみ線は昨年通ったのですが、そこよりまだ奥に行くそうです。biroさんが詳しいですよ。家の近所の方のご先祖様も
魚を天秤棒に担ぎ夕方柴を立ち山の中で夜を明かし宮が原に行ったそうです。ちなみにボテー衆とは牛や馬を売買する方ではなく
魚を担いで売って歩く方達だと、近所のおじいさんが
本日私の所へ来て訂正していきました。
宮が原の人達にとっては仁科に下るよりも宇久須に下る方が
早かったそうです。今とは道路事情が違いましたから。
私もくらみ線は昨年通ったのですが、そこよりまだ奥に行くそうです。biroさんが詳しいですよ。家の近所の方のご先祖様も
魚を天秤棒に担ぎ夕方柴を立ち山の中で夜を明かし宮が原に行ったそうです。ちなみにボテー衆とは牛や馬を売買する方ではなく
魚を担いで売って歩く方達だと、近所のおじいさんが
本日私の所へ来て訂正していきました。
宮が原の人達にとっては仁科に下るよりも宇久須に下る方が
早かったそうです。今とは道路事情が違いましたから。
Posted by カネジョウ at 2008年04月10日 22:36
at 2008年04月10日 22:36
 at 2008年04月10日 22:36
at 2008年04月10日 22:36日本昔話しの 世界ですね~♪
またまた 読み入ってしまいました。
早く寝ようと思うのですが~・。。・
またまた 読み入ってしまいました。
早く寝ようと思うのですが~・。。・
Posted by あび at 2008年04月10日 22:44
あび様毎度です。呼んでいただいてありがとうございます。
こういう昔話もどんどん失われて行きますので、どこかで
残してあげなければなりません。昔を知っている人は
どんどんお亡くなりになっていますので。
こういう昔話もどんどん失われて行きますので、どこかで
残してあげなければなりません。昔を知っている人は
どんどんお亡くなりになっていますので。
Posted by カネジョウ at 2008年04月11日 18:41
at 2008年04月11日 18:41
 at 2008年04月11日 18:41
at 2008年04月11日 18:41