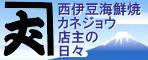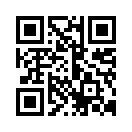2015年02月03日
柴地区のやいかがし

今日は節分です。今年も昭和15年頃までやっていたという やいかがし を
再現してみました。以前書いた説明文を下に載せます。
長文ですので気をつけてください。
子供の頃は私の地区でも各家で子供達の為にお菓子を撒きましてそれを
拾いに歩いたものでした。畳の上にお菓子をばらまきそれを夢中で拾ったものでした。
衛生上よろしく無いという理由で無くなったのかな。袋のまま撒けばいいと手思うのですが。
復活したい行事です。
以前節分の時に焼いた鰯を玄関先に竹でさして飾り
魔除けにしたという話を書きました。
やいかがし と言います。
そしてそれは浜区と芝区のことで入谷地区ではやっていなかったと
書きました。
そしたら芝区の古老が芝区は違うと言いました。
その話を書きます。
芝地区の古老の話だと芝地区のやいかがしは
いわしでは無くさんまを使ったという。
昔 この辺の漁師は紀州まで出かけ
向こうに泊まり込みで夏さんまを捕ったという。
漁法は流し網漁 網の位置を知るために
一メートル四方の板を網に付けその上に
ランプを乗せたと古老は言う。朝になると
若者はすすで汚れたランプのホヤを磨くのが
仕事だったという。この漁師さん捕ったさんまの一部を
持ち帰り地元の人たちにおかずとして分けたという。
もちろん販売もしただろう。どうやって保存して
持ってきたのだろうという質問に塩漬けではないかと答えた。
夏の物を正月まで取っておいて、正月に三枚におろして
切り身にして神様に供えた。その後はほうろく鍋で煎って
食べたという。そういうわけでサンマの頭が残る。
それを節分の時に使うわけである。
サンマを使うのは比較的お金が有る家でその他の家は
鰯を使ったという。
今は芝地区でも柊を植えてある所はほとんど無い。
それは使わなくなったからこいだだけ。
昔は皆植えて有ったという。
やいかがしを玄関に飾るとある言葉を外に向かって
言ったと聞きました。。
やいかがしにそうろう
なかなかにそうろう
隣のおばあが屁をひった
うーんくさい
やーんくさい
この後豆をまいたそうです。
「となりのおばあが」の処は
その家々で変えたそうです。
たとえば私の処ですと
隣が弁天という屋号の家ですので
「弁天のおばあが」となるわけです。
例えとはいえ弁天の関係者の皆様
申し訳ありませんです。
そうすると弁天の家では
「カネジョウのおじいが」
と言い返す時もあったそうです。
あくまで例えですのでお間違いなく。
これは悪口でも何でもなく
ごく普通にやっていたそうです。
焼いた鰯やサンマを飾るのはその臭いで鬼を家の中に
入れないという意味があったそうです。
もしかすると屁をひってくさいから
家に鬼は入るなという意味かも
しれませんね。