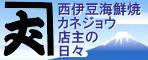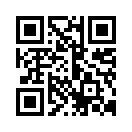2018年01月20日
安政の大地震についての口頭記録

写真は1月19日の宇久須神社 椿寒桜です。満開にはまだまだです。
以前防災関係の面で以前の津波の資料を探していたのですが
郷土研究会の先輩からの助言で探すことができました。
以前から疑問に思っていたことがいくつか解決したこともあります。
又聞いていたこととは違うことも書いてあり非常に勉強になりました。
広報 賀茂村 第80号より
安政の大地震についての口頭記録
話し手 古屋キワ女 (当時96才)
聞き手 宮石貢氏(当時45才)
年月 昭和10年4月
場所 キワ女の自宅
状況 この当時 失明していたが壮健で意識は明瞭だった。
安政大地震は、安政元年霜月4日4つ刻(1854年12月24日午前10時に起きた。)
当時古屋キワ女(古屋武雄さんの曾父母)は、神田の番匠屋(長島謹吾さん宅)
で養われていたが、口述記録はこの時の記憶を宮石貢氏が書き留めておいたものです。
聞き出した内容は断片的なものですが次のようなものです。
(地震について)
神田の公民館の裏の大岩はこの地震の時、山から落ちてきた。
また大道(今の村道)が砕けた。
発多沢の近所は大きく砕けた。
地震中「ドンドン」という音が響いた。
番匠屋(長島謹吾さん宅)の母は家がゆれて庭にころげ落ちた。
清水(宮石英夫さん宅)や隣屋(山地光彦さん宅)の老人は、向山の藪の中に泊まりに行った。
地震になる前の天候は、雨になるか、とにかくトロなぎだった。
寺の石塔が倒れて、何本も砕けた。
御座松(神田背戸山、稲荷岩の上の山頂にあったが、今は枯れてない)に、
この年10月13日(地震の前)と思うが、大きな火の玉がとんだ。
背戸河原にも大岩が落ちた。
小さな地震は、この年いくつもあった。
(津波について)
大きな地震だった。その間に「津波だ」という村の人たちの話声を聞くことができた。
津波は、郷村の下(旧役場の上の交又路)まで、押し寄せている。
宇久須川をさかのぼって、大明神さん(宇久須神社)まで、波先がきた。
浜の現在のやいど付近まで波先がきた。
神田の大屋では、田3反部(約30a)が流され、芝の奥(鈴木利彦さん宅)
では、うまやの天井に子牛が2匹、水に浮いて水が増えるたびに、上へ上へと上がってきた。
大川(宇久須川)は、すっかり赤にごりになった。
浜では、祭りのもちをついたが、ほとんど流してしまった。
清水(宮石英夫さん宅)では、浜に出してあった炭をたくさん流した。
深田と米埼でひろった炭が、600俵からあった。
底魚の大きなものが干上がった。どこの浜へも、4~5尺(1.2m~1.5m)のものがあった。
不来ケ坂のふもとに牛がたくさんつながれていた。
波が高く慈眼寺の前で波がうった。
安良里では、小さな家をたくさん流した。
立沢洞まで、船が波のためにうち上げられた。
(資料は宮石英夫さん提供)
Posted by カネジョウ at 21:03│Comments(0)
│郷土研究