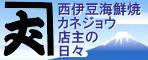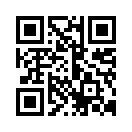2008年04月17日
異説 お船のこと

先日 地元の某先生より電話が有り、出崎神社の古い船を町の文化財に
指定したいから写真は無いかということでした。
現在出崎神社にはお船が三隻有りますが、11月の祭りで使うのは
新しい方の2隻。一番古い船は社の中にビニールにくるまれて保存され
写真がありません。そこで今度教育委員会から柴区長に依頼して
古いお船を外に出し撮影する事にしました。その時は出すのを手伝い撮影します。
出崎神社には江戸時代の物だというお船が有ったと言いますが
今はありません。どこにいったのでしょうか。
色々聞いてみると、捨てられたと言うのが正解でしょうか。
終戦までは社の中に有ったそうです。
ただ古くて損傷が激しい物でいつのまにか社から出されて、
社の裏に野ざらしにされたそうです。
そしていつのまにか無くなった。損傷の激しい物を野ざらしにしたら
朽ち果てるのはあたりまえです。
ゴミとしてかたつけられたのでしょう。
下に昭和51年に書かれた文章を載せます。
古老の話から見ていくと、11月の祭りが行われなくなってしばらく立ち、
城福寺の和尚さん 私の隣の
弁天の浅賀先生(両方とも故人)が柴子供会を復活させ、
昭和50年11月に祭りを復活させた頃の話です。
最後の方に出てくる糀屋のおじいさんが作った船もこの祭りがきっかけでした。
この当時猿っ子はまだ復活していません。
私が隣の池田先生から依頼され、猿っ子の最後の継承者松野金作さんの
踊りを撮影したのは昭和50年でした。
撮影機材は池田先生のものでした。昭和50年11月はとりあえず11月の
祭りの復活と言うことではじめました。
当時の柴子供会の総会資料を引っ張り出して調べたら
行事名「おみこし祭り」になっていました。
柴区の酒屋さんカネマス商店で空の酒樽を2つ分けてもらい父兄の協力の下
飾り付けと担げるように作りました。
これは男の子達が元気にワッショイ ワッショイと担ぐ物。女の子用にと
下記の文章に出てくる大下の7代前の
大工さんが作った船をみんなで持てるように台を作り持ちました。
出崎神社を出て柴の中道に入り当時運搬船八王丸を
回していた八王さんの家の前に来たときに女の子達が
「私たちも男子と同じようにワッショイやりたい」と言い出しました。
私は大丈夫かなと思いながらも「じゃあ、ちょっとだけだぞ。」と言いました。
小学生の女の子達は喜んでワッショイ ワッショイと
男子のまねをして船を持ち上げました。そのとたんに船の部品が周りに飛び散りました。
木で作った奉納用の船である。
まさか御輿として担ぐことなど想定してあるはずもありません。私たちは急いで止めさせて
部品を拾い元に戻しました。
この話を聞いた糀屋のおじいさんが「それじゃあオレが担いでも壊れない船を造ってやるよ。」
と言ってつくってくれました。
因みに糀屋のおじいさんは船大工でした。おばあさんは糀を作っては売っていました。
味噌を造るときはこの糀を使った物です。
昭和51年の11月の祭りでは男の子達は樽御輿を女の子達はお船の御輿を担ぎました。
その後樽御輿は姿を消して
お船の御輿だけになりました。近年もう一隻船が増えました。この後猿っ子踊りの
復活に話が向かっていきました。
異説 お船のこと 浅賀春吉 昭和51年発行文芸かも より
今を去る四百有余年、世は戦国時代と化した。
全国四百余州に群雄割拠して各々の領土拡張に専念した中で、
織田信長が現れたが本能寺で暗殺され、徳川と豊臣の二将の
争いになった。ここで雌雄を決すべく関ヶ原合戦となり、東軍徳川の
勝利に帰した。之より徳川十五代の礎が定まった。
何代の将軍の時代か詳かでないが諸大名を集結して、
今の隅田川で平和と五穀豊穣を祈念すべく櫂漕の競技ががあった。
此の時、人猿が出て来て踊った為に他船は只、唖然として漕ぎ手を
緩めた。その為、この船が優勝した。
その後、約一米半位の同型の船を造り、之を全国津々浦々に
放流した。このうちの一船が芝出先神社周辺の渚に漂着した。
船の中には、目出度歌詞の本もあった。この本は目出度に
始まり、皇帝桜揃、松揃、神揃、高砂等題字となっていて、
之を正月二日、歌初といって若衆が未明から奉唱し
十一月三日の天長節に、歌手宿老と言い、飾った船に乗り込む。
服装は娘等に思い思いに借用した。櫂数は十六挺。
歌手は今、皆物故されたが御参考に列記しよう。
(敬称略)、奥のお爺、橋の処の増太郎、店のお爺、
久治屋のお爺、半治丸のお爺等で、後を承継ぐ人がなかったので
今は目出度と皇帝のみ奉唱する。中途に於いて適当の船がなく
鳩首した。たまたま九州から島田様という方が当村へ漁獲に来ていて、
その船を借りて間に合わせた。島田様は不漁の為、引揚げたので、
その船を買い受け、続けていくことになった。
大正の初期の頃まで、毎年の行事として決行していたが、
その船も年が重なるにつれ、腐朽し、術もなく中絶の憂き目を
見たことも有る。この船は小生の子供の時は積船と呼んだ。
行事の時は、近所近辺から大勢の観客で浜いっぱいだった。
上げてある船酒盛。これが大繁盛した。
話は元に戻るが、柴に漂着した船は、伊豆の網代、
田子、安良里、遠州御前崎にも漂着したと聞く。田子、安良里の
行事は小生子供の時に確かに見たが何れも歌詞が同一曲なので
何れの歌人かが全国を行脚して演出したのではないだろうか。
小生達は何とか御船歌を続行したいと念願しているが、
肝心の船がないので考え続けている次第である。
それと歌手及び猿踊りの人選等区民一同この件で研究している。
又、時折民芸研究のためか、時々、遠方から訪れては
調査して帰る。
終わりに、現在神社に奉納されている二隻のお船は、
七代前の柴大下の大工の作。
他の一隻は屋号糀屋鈴木保三様の、
今年六月頃の制作によるものである。
(浅賀春吉謹書 七十八才)昭和51年当時
Posted by カネジョウ at 22:02│Comments(2)
│郷土研究
この記事へのコメント
>はじめまして、ステップが進みコメント出来るようになりました。
地域の祭りが廃れると、その土地の風習や伝統までも無くなって
しまいます。
我々地方に住むものは,都会地に住む人たちの故郷を守っています、地方に住む誇りを忘れずがんばりましょう。
地域の祭りが廃れると、その土地の風習や伝統までも無くなって
しまいます。
我々地方に住むものは,都会地に住む人たちの故郷を守っています、地方に住む誇りを忘れずがんばりましょう。
Posted by いそさん at 2008年04月18日 19:23
at 2008年04月18日 19:23
 at 2008年04月18日 19:23
at 2008年04月18日 19:23いそさん毎度です。さらなる進化おめでとうございます。
本当の地域に根付いた祭りは大切だと思います。
反面金を湯水の様に使い芸能人を呼ぶような祭りは
なくなってホットしています。本来の地元の人達だけの
祭りになって復活してほしいとも思います。
これからの観光はこういう古い言い伝え 伝統などが
必要になってくると思います。しかしこういう事はどんどん
埋もれていってしまいます。今のうちに残しておかなければ。
本当の地域に根付いた祭りは大切だと思います。
反面金を湯水の様に使い芸能人を呼ぶような祭りは
なくなってホットしています。本来の地元の人達だけの
祭りになって復活してほしいとも思います。
これからの観光はこういう古い言い伝え 伝統などが
必要になってくると思います。しかしこういう事はどんどん
埋もれていってしまいます。今のうちに残しておかなければ。
Posted by カネジョウ at 2008年04月18日 21:47
at 2008年04月18日 21:47
 at 2008年04月18日 21:47
at 2008年04月18日 21:47