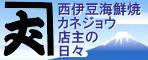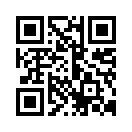2008年04月21日
本当の出崎神社祭典

写真は昔の宇久須の湾
11月3日の出崎神社祭典。お宮で猿っ子踊りを奉納。江戸時代に宮の後ろに流れ着いたと
言われている船を模した物を担いで柴区内を練り歩く。
一度廃しされたのを復活させたのだが、元々の祭りを知らないまま復活させた。
それが今に至っている。では、本当の11月3日の出崎神社祭典とはどんなものだったのだろうか。
当時を知っている方々に聞いてみた物を書き記しておく。
大正15年生まれの私の父は、出兵まではやっていた。と言っている。
その様子は現在の祭りとはかけ離れた物だった。
一度は再現してみたい物である。
昔は11月3日の祭りが近づくと出先神社の帳屋と松の木の間に
縄を張って櫓を漕ぐ練習をした。その松も今は無い。
切り株だけは残ってる。祭り一週間前から商売止め。
男しは船作り。女しはお飾り作り。船の舳先とともをのばし やかたをつける。
そしてみんなで花や猿っ子を飾り付けた。今の祭りに使うお船はその飾り付けた姿を今に残している。
普段はあんな姿では無い。感覚としては今は無き宇久須神社祭典の時の柴区の屋台と同じ。
宇久須神社祭典の時は普通の屋台を船のように作って引き回す。
祭り当日になると午前10時頃、宇久須の湾内に船を出す。
この当時は楽しみと言ったら浜区の人形三番叟か お船しかなかったから
宇久須の海岸は大勢の人が出ていた。昔は出先神社の下から
越までひろーい砂浜だった。
櫓は十六挺 若衆16人位 歌手宿老6人 若がしら猿っこ と乗り組んでさ。
御唄に合わせて櫓を漕ぐ。最初は御唄もゆっくりだから
漕ぎ手もゆっくり漕ぐ。湾の中を二周も三周もしただろうか。
陸に居る群衆の中からぼろぼろの服を着た若い衆が数人現れる。
手には破れた笠を持っている。これを振って船を招くようにしながら
「おかこい おかこい」囃し立てる。そうすると
船の中から猿の扮装をした若者が出てくる。猿の格好と言ったって
全身赤い服を身にまとっているだけ。
ここで御唄はは少し早くなる。それに併せて猿っ子踊りが
始まった。今は子供が踊るから一回しか踊らないが
昔は若い衆が踊ったから何回も何回も繰り返した。
まあ、そうは言っても20分位だった。
それが終わるとつんで有った オキダの糀ミカンを
浜にいる人に投げて廻った。
それで終わり。後は方付け。組んであったヤグラや舳先 ともの飾り等を
ばらして元に戻す。これが午後5時頃。船の置き場は城福寺の参道の下だった。
藁屋根の小屋の中にしまった。
その船も戦争が終わったら安良里の定置に売ったという。
昔、柴の宮のうしろにながれついた船は沖の宮さんに打ち上げられたと言われている。
だから柴衆は新船を作ると投げ持ちの前に沖の宮さんにお参りに行く。
船が大きい場合は、沖から拝む。
Posted by カネジョウ at 23:42│Comments(0)
│郷土研究