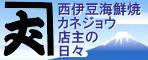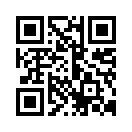2008年11月05日
柴区猿っこ踊り

11月3日朝8時30分より西伊豆町宇久須柴にある出崎神社(八王子神社)でお唄の奉納と猿っこ踊りの奉納が
行われました。
踊りは 次の4部から成っている。
1.立ち踊り 2.扇踊り 3.鯨突き踊り 4.逆立ち踊り
まずは、女の子達の猿っこばやし。最初はなかったのだが途中女の子達が
男子だけじゃずるい。ということになり あるきっかけで作ってもらって今にいたる。
昔は子供ではなく青年男子が踊ったのでこういう意見はでなかったのでしょう。
柴子供会の子供達が踊るようになってからですね。
どんど焼きの時も男子だけ泊まったのですが途中女子の泊まらせろということになり
父兄の協力の下部屋をわけて女子も公民館に泊まるようになりました。今はないですが。

お唄保存会のメンバーです。猿っこ復活の前はお唄の奉納だけが祭典で
行われていました。

立ち踊り 立ち踊りは、手をかざし、鯨が沖に居ないか探す所作

扇踊り 扇踊りは、金地に日の丸の扇を採り、
招くような所作があるが、これは次の鯨突き踊りと連鎖し、鯨を招き寄せる踊りと見える。



鯨突き踊 鯨突き踊りは、銛を採って鯨を突く所作の踊り


逆立ち踊り 逆さ踊りは逆立ちになって見せる物で、
地元では去るの反対来るを逆立ちで掛けている踊りと解釈している。
この逆立ちが大変です。復活当時私ともう1人の方にやれと言う事になりました。
当時子供会の指導員をしていた関係からです。
当時20代前半。しかし、これはしんどい。結局子供達に頼もうじゃ。というところにもっていってしまいました。
そして柴子供会のメンバーに「頼むぞ」。こうして無事猿っこ踊りは子供達に受け継がれる事になりました。
めでたし めでたし。



終わると父兄からおひねりが雨あられとふりそそぎます。
特にじいちゃん ばあちゃんが大活躍。
子供達は必死でかき集めます。

関連記事
沖の宮さん
本当の出崎神社祭典
異説 お船の事
猿っこ踊り
御船神事と安良里擢歌史考
お船
柴区出崎神社祭典
Posted by カネジョウ at 21:08│Comments(0)
│郷土研究